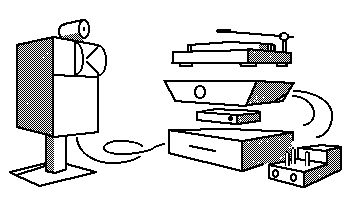
コンポを補佐したり、音質を調節するためにいろんな物が利用されます。
これらをアクセサリーといいます。
アクセサリーは大きく以下のように分けられます。
- 電気信号の伝達を補佐する 各種ケーブル、安定化電源、アース、など
- コンポへの物理的振動の影響を調節する ラック、スタンド、インシュレーター、ボードなど
- 室内音響を調節する ルームコンディショナーなど
こんなことで変わるのか、というようなことで音は大きく変わります。
そういうところが面白いところです。
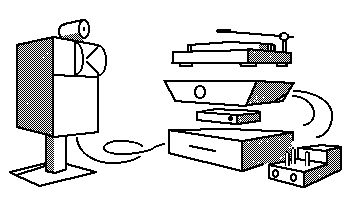
コンポを補佐したり、音質を調節するためにいろんな物が利用されます。
これらをアクセサリーといいます。
アクセサリーは大きく以下のように分けられます。
こんなことで変わるのか、というようなことで音は大きく変わります。
そういうところが面白いところです。
コンポだけでは音は出ません。
ここではアクセサリーについて紹介します。(2005.08.09. 改訂 2003.09.02.版)
コンポについてはこちら→COMPORNENTS
インターコネクトケーブルは、いわゆるライン信号を伝達するケーブルです。プレーヤーとアンプをつないだりするのに使います。民生用のRCA接続用のケーブルと、業務用のXLR接続用のものが一般的です。微弱な音楽信号を扱うので、電磁波などによるノイズへの対策をしているものが多いです。
AC Design/basis 1.4:情報量が多い銀線ケーブルです(2003.11.04.追記しています)。
つないで再生ボタンを押した次の瞬間にホールトーンの再現性、空気の感触から違うと感じました。
とても写実性が高く実体感のある音です。オーケストラの奥行きも出やすい印象です。
ただ、高解像度の写真を見るようで、美しいのですがよそよそしいと感じさせるところがあります。
あと、Spase&Timeと比べたら若干低域が薄いかなぁ、、引き締まってるのか?
現在、Odeon-LiteとSM-SX100をつなぐのに使っています。現状では、この経路の音が一番オーディオ的には高音質だと思います。
Spase&Time/PRISM55-i:クリアな音のケーブルです。
透明感が高くコストパフォーマンスの高いケーブルといわれています。
レスポンスがよく、かつ木目細やかな感触ですが、やや中域が他のケーブルに比べると薄い気がします。
現在、basis 1.4と比較しながら、Odeon-LiteとSM-SX100をつなぐのに使っています。
basisと比べると、水彩画のようなやさしい感触があって聴きやすいです。しかし、basisでいくことになるかなぁ。微妙。
今後は、VRDS25xsとSM-SX100の直結に使ってみようかと思ってます。
これはOdeonLite導入前の使い方です。25xs内蔵DACの硬さが中和されます。
basis 1.4と比較検討の結果、メインの席を譲ることになりました。
basisと比べると、水彩画のようなやさしい感触があって聴きやすいです。
使わないでいるのは、ちょっともったいないのですが、、。
AUDIOCRAFT/MX-100:きっちりした感じの音です。
堅実な音というか、なんとなく正確な音が出てるかな、という感じがします。
どっちかというとかたい音かな。和やかな感じはしません。
現在、TU875の出力からSM-SX100につないでいます。
SAEC/SL-1903:厚みがある音がします。
ハードな音ですが、ウォールサウンドというか、どっちかというとしっかり定位を出すというよりは雰囲気重視なのかな。
現在、VRDS-25xsのRCA出力からTU875への出力に使っています。
TU875からの出力はもともと若干定位が甘いので、さほど気になりません。
ortofon/Reference 8NX:バランス接続用です。
けっこう高級なケーブルで、音色はノーブルといいますか、高品位で豊かな音がします。
以前はVRDS-25xsからのバランス出力に使っていました
しかしセッティングの改善によってアンバランス接続の方が音が良くなったので、現在は使っていません。
これもちょっともったいない。
audioquest/SIDEWINDER:シンプルな構造の単線ケーブルです。
工作が容易で使っていたことがありましたが、やや音像が膨らみがちで響きが明るすぎるため、現在は使っていません。
Belden/STR412:柔らかい音質のケーブルです。
うちではコンポの性格に合わないようで、ふわふわ霞んだような感じになりました。現在使っていません。
デジタルケーブルは、デジタル信号を伝達するケーブルです。オーディオで使われることが多いのは同軸ケーブルと光ケーブルですが、他にも種類があります。同軸ケーブルはインピーダンスが正確に決められています。光ケーブルよりも同軸ケーブルの方が音が良いことが多いようです。デジタル信号だから音は変わらないはずという意見もあるでしょうが、オーディオというものはそう単純ではありません。デジタル信号伝達でも音が違うことについて、いろいろ理論的な説明も考えられています。
SAEC/EFF-2000:普通の音です。
VRDS-25xsのデジタル同軸出力からOdeon-Liteへの出力に使っています。
なんというか、可もなく不可もなくというか、うちの同軸デジタルケーブルの中では一番きっちりした音という印象です。
特に何がすごいというとこもないように思いますがコストパフォーマンスは良さそうです。
XLO/Ultra 4:クリアで明るい音の同軸ケーブルです。
しかし、高域に若干癖があるというか、独特の響きがあるような気がします。
あと、やたらプラグがきついのが使いにくかったかな。個体差があるかもしれません。
現在は使っていません。
Belden/STD695:ソフトな音の同軸ケーブルです。
ベルデンはソフトな傾向のようで、デジタルケーブルも同様です。
中域が厚めでソフトにふわっとした包んでくれる刺激のない音を求める向きに向いているように思います。
うちのシステムには合いません。現在使っていません。
SAEC/OPC-M1:光ケーブルです。
光ケーブルは低温が緩くなるといわれますが、これも御他聞にもれません。
光ケーブルは、あまり製品によって大きな違いが出ないという印象があります。
VRDS-25xsからMDプレーヤーにつないでいます。
アンプからスピーカーに信号を伝達するケーブルです。インピーダンスは低いので、特にシールド等のノイズの対策はしていないものが多いようです。やはりケーブルによって音は違います。ケーブルの構造や使っている材質によって電気的な特性が違ってくるためです。
5.5mmスケアキャブタイヤ:送電に使われる業務用のごついケーブルです。
コストパフォーマンスが高いと言われています。中域が厚めといわれます。
こちらでは、片チャンネルに5mのラインを2本、バイワイヤで接続しています。
1本よりも2本の方が音が引き締まりエネルギー感が増す印象です。
他のケーブルをいろいろ試してみる手もあるのですが、5×4=20mにもなるのでなかなかやる気が起きません。
メートルあたり5000円でも、10万円になりますから。だったらキャブタイヤのままでいいかなぁ、なんて。
やってみないとわかりませんけどね。
JBLの純正が良さそうなのですが、近隣では売っていません。
引っ越してコンポの配置が変わり、現在は片チャンネル2mのラインです。
ケーブル短縮による音質改善が見込めるかとも思われましたが、床など他の要素によるマイナスが大きく、改善の度合いははっきりしません。
Space&Time/omni8:クリアな音質に定評があります。
メインスピーカーの端子とスーパートゥイーターをつなぐのに使っています。
これもコストパフォーマンスが高いと言われています。
一般的な赤黒ケーブルでは柔らかくて太い感じの音になりますが、omni8だと細やかですきっとした感じになります。
しかし中域は薄い気がするので、メインスピーカーに使う気はあまり起きません。
一般用赤黒スピーカーケーブル:よくあるやつです。
TU870を使う時に使用しています。
このときはシングルワイヤーで接続します。ちなみにTU870は2台を左右に割り振って使います。
最近のコンポは、電源ケーブルが交換できる仕様のものが増えてきています。電源ケーブルで音が変わるというのは驚きですが事実です。
4N2φ銀単線電源ケーブル:ネットで知り合った方から安価で譲っていただいた自作ケーブルです。
これはかなりの効果がありました。音質を全体的に底上げするという印象で、ぐっと安定感が増しました。
電源系の改善というのはそういう感じなのかもしれません。
透明感、立体感があり、音の鮮度、実在感、柔らかさとシャープさ、全てが改善されました。
VRDS-25xsとSM-SX100に使っています。
かつては見過ごされがちだった領域ですが、ここ数年間で電源系のアクセサリーは非常に増えています。電源タップで音が変わるのを意外に思われる方もおられるかもしれませんが、実際変わります。屋内配線から見直す人もいます。
うちでは桜材の塊を土台に使った自作の電源タップを使用しています。
効果のほどは、微妙です。市販の一般家庭用タップよりは若干音が落ち着いたような気がしてますが。
今後何か市販の製品に変えてみようと思っています。
一般家庭用タップでも、ものによって多少音質に差があるようです。
桜材電源タップは引っ越しに際して紛失。
現在、市販の家電用電源タップにて送電中。なんとかしなくちゃ、って感じです。
パソコンなどのノイズ対策に使う一般的な市販のOAノイズフィルターをSM-SX100とVRDS-25xsに使っています。
うちの環境では、多少効果があるように思いました。
アース環境を改善するオーディオ用のアクセサリーは多数販売されています。
意外に思われる方もおられるかもしれませんが、物理的な振動は音質に影響します。
まずスピーカーへの影響ですが、電気信号を空気の振動に変える装置であるスピーカーは、それ自体は振動しないことが理想です。振動することで、特有の響きが再生音に加わってきます。完全に振動しないスピーカーは現実的にはあり得ないので、振動を調節するアクセサリーが必要になります。
プレーヤーやアンプに伝わる振動も音質に影響します。コンポは素子の集合体ですが、素子に振動が伝わることで電気信号が生じます。素子自体にインピーダンス、インダクタンスがあり、物理振動を電気信号に変えてしまうのです。また、CDやレコードのプレーヤーには回転する部分や振動する部分があり、外部からの物理的な振動はこれらの動きに影響を与えます。プレーヤー自体が振動の発生源でもあります。プレーヤーやアンプの振動対策も、意外なほど重要です。
アクセサリーというのではないですが、床の状態は音質に結構影響します。
うちは鉄筋コンクリートに薄いシートを張ったような床なので、比較的振動に強いようです。
VRDS方式のCDプレーヤーを使っていますが、床のおかげで性能を引き出すことに成功していると思います。
2004年の春、引っ越しました。床はコンクリートから一般的なフローリングに変わりました。
オーディオ環境としては、大きく悪化したと言っていいでしょう。
低音が締まりなく膨らみ、それに伴って音像、音場、空間表現もモヤがかかったようで見通しが悪くなりました。
ボリュームを上げるのが苦痛になりました。
これは僕の好みの正反対に振れた状態です。
コピーコントロールの問題に係りきりだったこともあって悪条件のままで放置していたのですが、2005年夏、対策を開始しています。
ラックは、ホームセンターに売っているマンテンのフレームと、合板やMDF板を組み合わせて使っています。
しっかり組み合わせると、ガタもなく叩いても響かないラックになります。
しかし、しょぼいので製品の購入を考えています。
2004年の春、引っ越しました。
以前のコンクリートの床では、さしたる問題もなくマンテンフレームラックでいい音を聴くことが出来ました。
しかし現在、より高度な振動対策能力が問われる環境では問題が生じるかもしれない、と考えるようになりました。
スピーカー下の対策が優先なので、そちらが形になったらその上で考えていこうと思っています。
TAOC/MST-40H:鋳鉄製のスタンドです。
JBLの純正スタンドのモデルになったものです。
芯のあるメリハリの効いた音になると言われています。
弦楽器とか聴いても問題ないと思いますが、人によっては音がきついと思われるかもしれません。
ある程度の高さがないと4425mk2のようなスピーカーでは低音が膨らんでしまいます。
床に座って聴くなら30cm程の高さの方がドライバーの高さに耳の高さが合うのですが、、。
迷った末、40cmの高さがある40Hにしました。
Audio Replus/OPT-1:石英ガラスのインシュレーターです。
小さな石英ガラスの円柱です。そのルックスの印象そのものの音がします。
音像の間の空間に漂っている微弱なノイズが消え去って、透明で見晴しのいいクリアな感触の音になります。
そういった効果もあって、音場に奥行きが出る感じです。
音色も反応が速くなり、微細なニュアンスが見えてくる感じです。
CDプレーヤーのVRDS-25xsの底板を3点指示で支えるのに使用しています。
J1-Project/A40R(青丸):特殊素材のインシュレーターです。
定番のインシュレーターです。
青くて薄い円盤です。素材はゴムのようなプラスチックのような感じで、NASAで研究されたものだそうです。
振動の影響を減らして、そつのない音にする効果があります。重たいコンポの方が効果が出るそうです。
しかしVRDS-25xsに使った感じでは、これだけで突き詰めていくとなると限界もあるようです。
アンプのSM-SX100に使用しています。
J1-Project/SP35S(黒コーン):特殊素材のインシュレーターです。
黒い小さなコーンです。青丸よりも堅い素材です。
VRDS-25xsに使ったところ、青丸よりも振動を整理する力が強いようで、より音楽の情報を引き出しました。
しかし若干鮮度が失われるというか、落ち着き過ぎる感じになりました。
現在は使用していません。何でもそうですが、使いようです。
しばらく使っていませんでしたが、引っ越して床がコンクリートからフローリングに変わり、床に御影石ボードを導入。
現在、その御影石ボードとスピーカースタンドの間に使用しています。
不要な振動を整理するのにかなりの効果がありました。
↓
ユーザーレポート(石匠運慶 御影石オーディオボード)
御影石ボード:石材店で作ってもらいました。
御影石はそのまま使うと石の響きが強くて使えません。ガラスが割れる時のような音色が付いてきます。
しかし叩いても鳴かないようにダンプ材を併用するなど対策すれば、オーディオボードとして使えます。
安価ですから、コストパフォーマンスが高いです。
うちでは、VRDS-25xsのボードとウェイト、4425mk2のウェイト兼T900Aのボードに使っています。
安くて使いやすい気がするので、さらに使用する場所が増えるかもしれません。
石匠運慶/御影石ボード:ネット通販の御影石ボードです。
2004年の春、引っ越しました。
床がコンクリートからフローリングに変わり、オーディオ環境としては、大きく悪化しました。
低音が締まりなく膨らみ、それに伴って音像、音場、空間表現もモヤがかかったようで見通しが悪くなりました。
ボリュームを上げるのが苦痛になりました。
2005年の夏、対策としてスピーカースタンドの下に導入しました。
サイズは50cm×50cm×3cmです。
かなりの効果がありました。ボリュームを上げても落ち着いて音楽に浸ることが出来ます。
↓
ユーザーレポート
合板・MDF板
スピーカースタンドの下にMDF板を使っています。
振動対策なのですが、どの程度効いているかは、正直、未知数です。
ラックの棚板として合板・MDF板を使っています。
一枚板ではなく数枚重ねて使うほうが、音が落ち着くような気がします。強度の問題かも。
ゴムシートを振動を吸収するダンプ材として使用しています。
VRDS-25xsの天板にウェイトを載せるのに、クッションとして0.5mm厚を使用しています。
4425mk2のエンクロージャー天板のウェイトの下には3mm厚を使用しています。
昔は、あちこちに多用していましたが、現在のシステムでは使い過ぎは良くないです。
布もダンプ材として使用できます。
スーパートゥイーターと金属脚の間に布を挟んでいます。
効果のほどは、若干硬さがとれる気がしますが、ちょっとはっきりしません。
VRDS-25xsの天板のウェイトに布やセーム革を使用したことがありますが、種類によって音が違い興味深いものでした。
ホームセンターで売っているいろいろな素材がインシュレーターとして使用できます。
ゴムシート、硬貨、木片、紙など、いろんなものをインシュレーターとして使っていました。
使うものによって音の感触が違います。
家電店でもオーディオ用として安いインシュレーターが売られていて、いくつか使ったことがあります。
しかし大抵はホームセンターで買える素材と五十歩百歩だと感じます。
以前はコンクリートブロックをスピーカースタンドに使用していましたが、現在は使っていません。
コンクリートは、使いようによっては面白い素材だと思います。
なるべく密度が高いものを重ねないで使うのが、うまく使うコツだと思います。
似たようなものでレンガがありますが、これはインシュレーターやスタンドに使うと濁りが出てうまくいきません。
僕はもっぱらウェイトに使っていました。
といっても、ミニコンポを使っていた頃のことですが。
音はスピーカーから出た後、リスニングルームに放たれます。音楽を聴く部屋の環境は千差万別です。すき間が多い木造の和室とコンクリートで気密性の高い洋室では、全く音の挙動が違います。ある部屋できれいに鳴っていたオーディオセットでも、違う部屋に持ち込むとひどい音で鳴る可能性もあります。
室内音響は最後の仕上げといわれることがありますが、状況によっては先になんとかしなければどうにもならないこともあります。特に問題になりやすいのは「定在波」です。高域で生じる定在波(竜鳴き、フラッターエコーといわれます)は簡単に対策できますが、低域で生じるものは非常にやっかいです。特定の周波数が増強したり、他の周波数では逆に減弱したりするため、再生音が不安定になるのです。聴くに耐えなくなることも場合によってはあります。
部屋の形態は、室内音響に大きく影響します。
うちは8帖のほぼ正方形の部屋なので、強い定在波が発生しやすい環境です。室内音響的には不利な形です。
吸音材を使用しないと、定在波がひどくて使い物になりません。
2004年の春、引っ越しました。
部屋の形状は、2.6m×(3.5m+2.6m)×2.6mです。リビングとダイニングが繋がっています。
以前の部屋ほどひどい定在波は見られないような、、。
もしかしたら、これは音量を上げていないことのほうが大きいかもしれません。
現在、フローリングの床の影響で音質が低下し、音量が上げられなくなっています。
音量を上げられるようになったら、2.6m×2.6mの影響が出てくるかもしれないと思っています。
2005年夏、対策を開始しています。
東京防音/GAC-1150・GAC-1010:高密度グラスウールを使った吸音材です。
高さ1mの高密度グラスウールの直方体とボードです。
みてくれが悪いのとかさばるのが問題ですが、うちではこれがないとどうにもなりません。
高密度グラスウールは、一般的なグラスウールとは別物です。
100Hz以下の比較的低い周波数の音を吸収する力が強く、定在波の減弱にかなり効果があります。
1150はスピーカーの後方外側に置いて、共鳴する低音の吸収を行っています。
これによって、定在波がかなり減ります。
1010はスピーカーの前方外側に置いています。
これは、低音の吸収と同時に壁からの中高音の二次反射の遮断も目指しています。
2004年の春、引っ越しました。
現在の部屋では、以前ほど大きな効果を発揮していません。
これはGACのせいと言うよりは、音量が上がらないため効果を発揮できない状況かもしれない、、。
1150はスピーカーの後方外側、1010はラックの後方に上下に積んで置いています。
スピーカーの後方は、カラーボックスを積み上げて本を詰め込んでいます。
多少は音の拡散吸収に効いているんじゃないかと思いますが、はっきりしません。
ただの壁とかよりはいいんじゃないかと思うんだけど、、。
床には、薄手の絨毯を使用しています。
リスニングポイントの後ろに毛布を張っています。
ちょびっと、音場感の安定に効いているようです。
引っ越し以降、上記のカラーボックスと毛布は撤去。
フローリングの床に絨毯を敷いています。